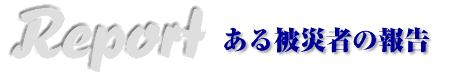
『被災』その1 |
|
その朝、大地が唸るような音で目がさめた。その瞬間、自分が何か乗り物の中で寝ていて、それがどこかに衝突したような凄まじい振動に襲われた。しかしその振動は、乗り物事故より遥かに長く、起き上がる事もできずに飛び交う家財を避けているうちに、自分が大地震に見舞われているのだと認識した。 揺れがおさまってから慌てて家族の様子を確認に急ぐ。幸いな事に誰もたいした怪我も負っておらず、とりあえず安堵する。近所にはほとんど倒壊してしまったような住宅もあったが、住人は救出されたようで、集まった人々の輪には笑顔もみられた。『家は壊れたがあれだけの揺れで命があったのは運が良かった、有難い事だ』、そんな思いからの笑顔だったと思う。 |
早すぎた『復興』? |
|
日が出る頃には私も家族もすっかり平静を取り戻していたと思う。自分たちがおかれている現状を冷静に判断できているつもりでいた。駅の南で火災が発生しているという話を伝え聞いたが、当然消火作業には消防があたるものと早合点し、自宅の点検と片付けをはじめた。『今日寝る場所だけでも確保しよう』そんなおごりがあったと思う。駅の方角に黒い煙りが立ちのぼるのを見ながら片付けに没頭した。 |
『被災』その2 |
|
もう昼に近い刻なのに空はいっこうに明るくならない。もとより停電で電気は使えない。思うように進まない片付け作業の手を休めたところに、駅前で店鋪を経営していた友人が訪れた。 「延焼を免れないので避難してるんだ」そういう彼に、「うちで良かったら使ってくれ」と応えると彼は険しい顔でこう言い返した。「ここだって安心はできないぞ、貴重品をまとめて避難するんだ」 彼は避難勧告に立ち寄ってくれたらしいが、その意味を理解できないでいた私に彼は続けた。「消防が機能していない。水がないんだ。消防車が来ても放水する水がないし消火や救助を求める人々が集まってパニックになってしまうんだ。」 はっと気付いて駅の方角を望むと延焼がさらに広がっているばかりか、他からも黒い無気味な煙りが何本も立ちのぼっていた。それが空を被ってまるで夕闇のようだ。暗かったのは落ち込んだ気分の所為だけではなかった。 |
『痛哭』 |
|
幸いにして延焼はまぬがれたが、通りを挟んだ向こう側まで火の手は迫っていた。地震による倒壊から延焼までの時間が短かった火元に近い地域では、生きたまま焼死したいわゆる『焼き仏』となられた方も多かったと聞く。揺れから難をのがれた喜びから、生存者である私達に油断があったのは事実である。その時が『非常事態』であることは充分に認識していた。だが『非常事態』に何をなすべきかがわかっていなかった。いや、『非常事態』に備えてすべき事がなされていなかったのだ。 |
『震災が残した教訓』 |
|
『非常事態』に備えてしなければならなかった事を考えるにあたって、注意しなくてはいけないのは『非常事態』には公的な手段によって維持されていた生活線(ライフライン)や救助システムは崩壊するということを大前提とすることである。つまり救助活動やライフラインの確保は地域で維持できるシステムにしなくては『非常事態』には機能しないという事である。 消防が機能しない事を前提に『消火・防火』の為のシステムを構築する。また、救急車がこない事を前提とした『医療処置』システム、レッカー等の救助隊がこない事を前提とした『救援・救助』システム、そして『生活用水』と『食料』『防寒具』などの備えを万全に整えることが、あまりに多くの犠牲者をだしたこの震災が残してくれた教訓といえるのではないだろうか。 |
|
禁複製 Copyright(C)1999-2018 TOYO Earth-Techno CO.,LTD. All Right Reserved.
|